オーストラリアで絶対行きたいおすすめスポット35選 ③
3回に分けたシリーズ↓
” 雄大な自然にあふれ、秘境や絶景スポットも数多くあるオーストラリアは、旅行先として絶大な人気を誇る。数多くの観光名所の中から、ぜひ1度訪れたいおすすめスポット35選を紹介!”(出典:msn)
の最終回で、11スポット。
ロード・ハウ島
シャーク湾
ユークラ国立公園

グレートオーストラリア湾

ヤラ・レンジス国立公園
マリア島国立公園
ワラマン滝
ディブローガーガン山

フレーザー島
デインツリー国立公園
レイクケーブ
3回に分けたシリーズ↓
” 雄大な自然にあふれ、秘境や絶景スポットも数多くあるオーストラリアは、旅行先として絶大な人気を誇る。数多くの観光名所の中から、ぜひ1度訪れたいおすすめスポット35選を紹介!”(出典:msn)
の最終回で、11スポット。
ロード・ハウ島
シャーク湾
ユークラ国立公園

グレートオーストラリア湾

ヤラ・レンジス国立公園
マリア島国立公園
ワラマン滝
ディブローガーガン山

フレーザー島
デインツリー国立公園
レイクケーブ
日曜日だというのに「あれ今日(通常、日本時間で月曜開催)?」といった感じで開催された
Chicago Bears:シカゴ・ベアーズの2016年シーズン15戦目(第16週)。
相手はプレーオフ戦線を凌ぎを削っているWashington Redskins:ワシントン・レッドスキンズ。
前回 ↓
” 雄大な自然にあふれ、秘境や絶景スポットも数多くあるオーストラリアは、旅行先として絶大な人気を誇る。数多くの観光名所の中から、ぜひ1度訪れたいおすすめスポット35選を紹介!”(出典:msn)
の続きで、今回2回目。
ルナ・パーク

スリー・シスターズ
ダーリングハーバー
ウルル
カカドゥ国立公園
12人の使徒

ゴールドコースト
ダンピア
レディ・エリオット島
メルボルン・クリケット・グラウンド

フレミントン競馬場
ブルー・マウンテンズ国立公園
予想どおりというべきか、VAN HALENの2016年は何事もなく過ぎ去っていきそうですが、
クリスマス(元のメッセージは宗教性を排したHappy Holidays)を迎え、メンバーの公式ページやら

Eddie Van Halenの愛犬(Kody Van Halen)やら

季節柄のメッセージがファンに向けられた中、「おっ!」となったのが、
公式ページのプロフィール画像に掲げられた(David Lee Roth 時代の)ロゴ ↙︎
しばらく直近の最新作 Tokyo Dome in Concert のジャケットに描かれた船であったかと思いますが
「いつの間に・・」といった感じで差し代わっていました。
” 雄大な自然にあふれ、秘境や絶景スポットも数多くあるオーストラリアは、旅行先として絶大な人気を誇る。数多くの観光名所の中から、ぜひ1度訪れたいおすすめスポット35選を紹介!”(出典:msn)
↑ なるセレクションを(登場順に)3回に分けて紹介したいと思います。初回は・・
ボンダイ・ビーチ
シドニー・オペラハウス
マークスパーク

ロッド・レーバー。アリーナ
グレートハリアリーフ
エーア湖

マウントフィールド国立公園
シドニー中心業務地区
ハマースレー山脈
ストーリーブリッジ

10月初旬「2017年2月24日リリース」とのことで記事にした ↙︎
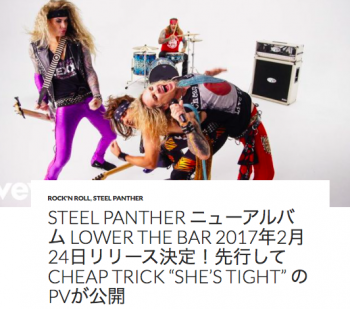
STEEL PANTHER 4作目となるフルレンスアルバム(除. ライヴ盤)LOWER THE BAR
先日、何気にSTEEL PANTHERの公式Facebookページ ↙︎ を眺めていれば・・

2017年3月24日に変更となっていました。
続きを読む STEEL PANTHER ニューアルバム LOWER THE BAR 2017年3月24日リリース変更。第2弾 “Anything Goes” が公開
“「QS Graduate Employability Rankings 2017」で世界中の「就職に強い」大学がランキング化され、世界一はスタンフォード大学、日本一は東大ではなく早稲田大学であることが分かった。
このランキングをまとめたQS(Quacquarelli Symonds)社は、高等教育やキャリア開発の情報提供を行っている。世界300大学の就職に強いかどうかという視点でランク付けしたもの。
評価項目は5つからなり、「雇用者による評価」、「企業とのパートナシップ」、「卒業生の活躍」、「雇用者と学生のコネクション」、「卒業生の就職率」から採点されている。
1位を獲得したのはスタンフォード大学。多種多様な民族や年齢の学生から構成され、シリコンバレーの発展に多大な貢献をしてきた大学である。
「雇用者による評価」と「卒業生の活躍」が満点となる100ポイントの評価を得た。
「企業とのパートナシップ」、「雇用者と学生のコネクション」についても90ポイント台となるトップレベルの評価を得て、堂々の1位を獲得した。
トップ30の大学を国別で数えると、フランス、シンガポール、スイスが各1、日本、オーストラリア、ドイツが各2、カナダが3、中国と英国が各4、米国が最多の13となっている。
民間企業との連携を積極的に行っている米国の大学の評価が高くなっていることに注目したい。”(出典:ZUU onlineから抜粋)
続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:就職に強い世界の大学ランキング( #4 シドニー大学、#11 メルボルン大学)