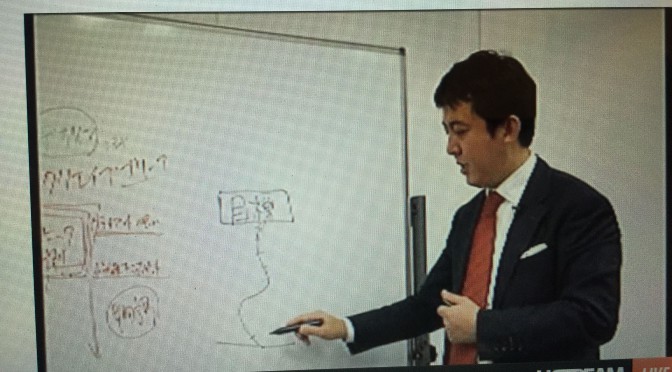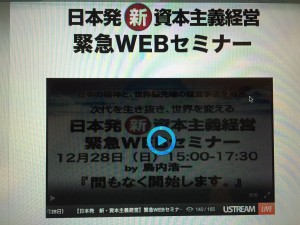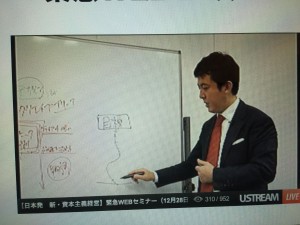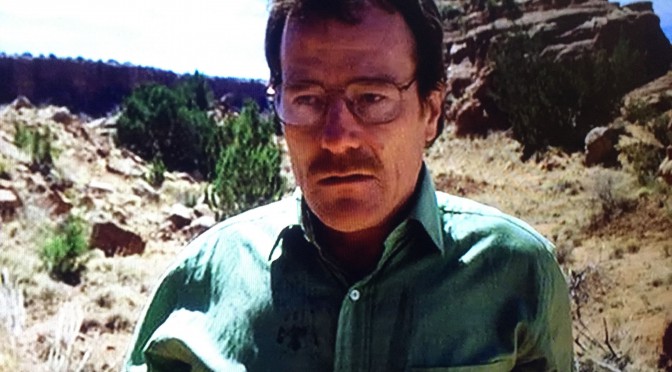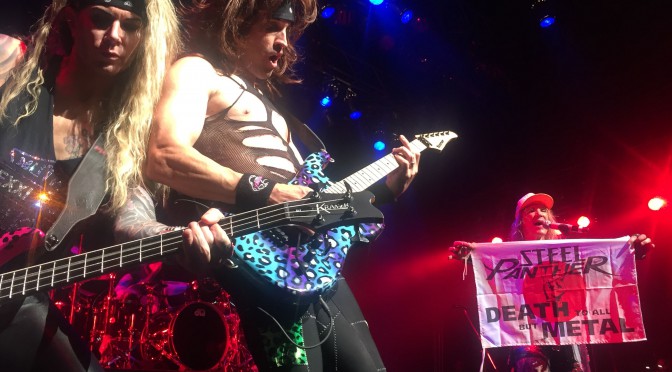9月に開幕したNFL、レギュラーシーズン最終戦@第17週。
1年前の最終戦は、地区優勝&プレーオフ進出の懸かった大一番で、都内で当該チーム(対グリーンベイ・パッカーズ)のファン同士による観戦会があって
昨年の模様 >> シカゴ・ベアーズも年内で尽きた <<
夜も開けていない頃に始発に乗ってワクワクしながら Kick Off の瞬間を迎えた覚えがありますが・・
1年経ってみれば、(対ミネソタ・ヴァイキングス)負けた方が地区最下位となる極端な展開。 続きを読む シカゴ・ベアーズ、地区最下位決定戦に尽きて5勝11敗で終戦:NFL 2014シーズン第17週 →
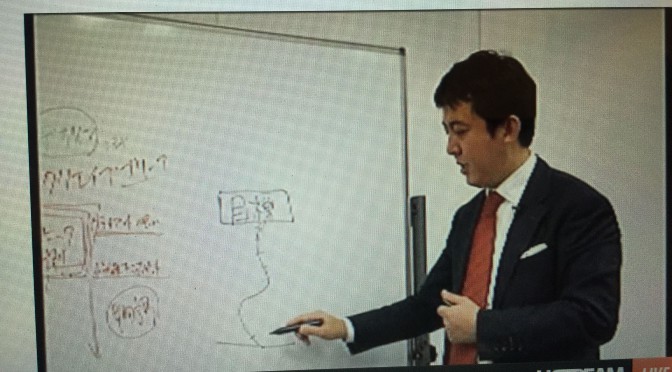
夏以来で、鳥内浩一さんのウェビナーを受講。
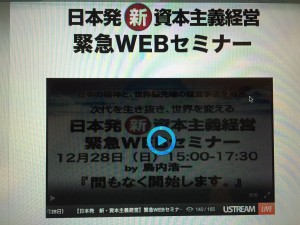 同じ内容は夏にも受講していますが、2015年のトレンドを読み込み、より深化した形で学べました
同じ内容は夏にも受講していますが、2015年のトレンドを読み込み、より深化した形で学べました
前回の模様 >> 渋沢栄一が説いた「信」、鳥内浩一さんが説く「八つの徳目」に見出す未来 <<
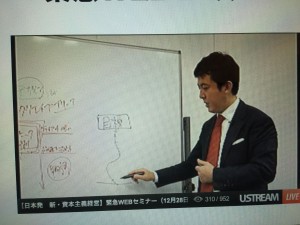 15:00〜17:30、19:00〜21:30の2回開催。内容への興味から両回受講しましたが、何れも約1時間の延長。その重厚感から2回目終了の22:30頃には、すっかりノックアウトされていました(笑)
15:00〜17:30、19:00〜21:30の2回開催。内容への興味から両回受講しましたが、何れも約1時間の延長。その重厚感から2回目終了の22:30頃には、すっかりノックアウトされていました(笑)
鳥内さんは、現在、受講中の池間哲郎さんの『日本塾』を運営されているリアルインサイトの代表ですが
もともと私が鳥内さんを知ったのは、全米No.1マーケッターであるジェイ・エイブラハム『マーケティング・マインドマスター・プログラム』のファシリテイターを務められておられての事。 続きを読む 鳥内浩一さんが体系化した時代の要請に応える経営のフレームワーク「十方良し」の経営学 →
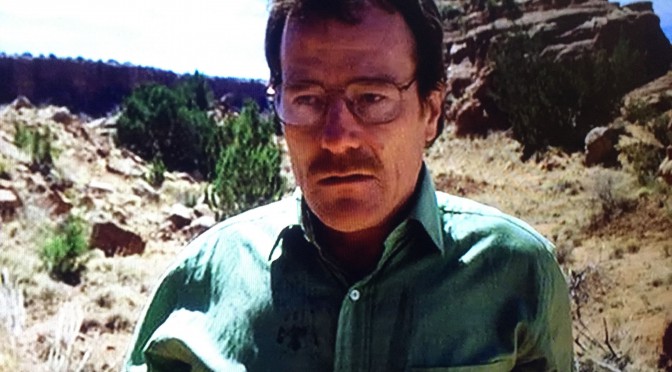
年末年始は海外ドラマ期!?
例年、旅行などの予定を入れない傾向から、レンタル店に顔を出す割合が高くなる年末年始ですが
特に海外ドラマなどの尺が長いものは、この時期うってつけですね。そんな背景もあり、
この前借りてみた『ブラックリスト』のつづきでなし、
>> ジェームズ・スペイダー主演の海外ドラマ「ブラックリスト」のさわりを見てみた <<
他方で気になった『ブレイキング・バッド』を手に取ってみました。 続きを読む ブライアン・クランストンが演じる化学教師のダークサイドな展開:『ブレイクキング・バッド』を見てみた →
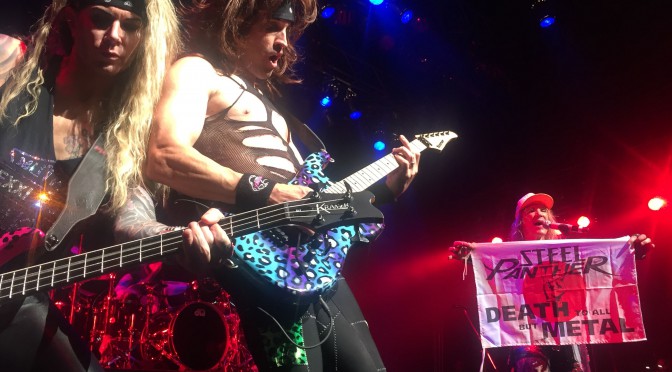

岡田斗司夫さん『僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない』を読了。
岡田 斗司夫 FREEex PHP研究所 2014-10-16
岡田さん本は『いつまでもデブと思うなよ』を読んで以来、以降、『評価経済社会』『評価と贈与の経済学』など
全作と言わないまでも、新刊を楽しみにしている著者で、それは腑に落ちる分析力にありますが、
この本は見事に期待に応えてくれました。
続きを読む 岡田斗司夫さんが説く、なんとなく気持ちのいい人生:『僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない』読了 →

街中を歩いていて、さほどChirstmas/クリスマスという感じは漂ってこなかったものの
やはり12/24-25は!という事で、クリスマスに3曲。
続きを読む Chris Rea “Driving Home For Christmas”ほか、Xmasな3曲 →


レギュラーシーズン残り2週(試合)となったNFL。
年明けから始まるプレーオフ進出の望みを絶たれたシカゴ・ベアーズの関心事は
来季の攻撃の司令塔QB(クォーター・バック)を誰が務めるのか。 続きを読む シカゴ・ベアーズ、今季を象徴するような顛末にて5勝10敗:NFL 2014シーズン第16週 →
「冒険」に出たものだけが、大きな果実を手にすることができる