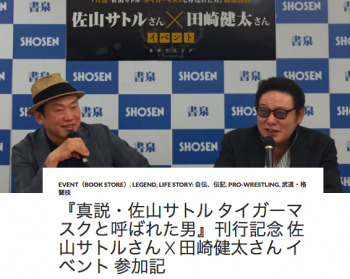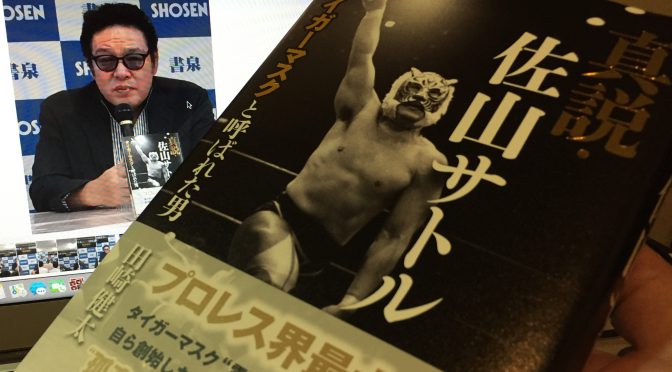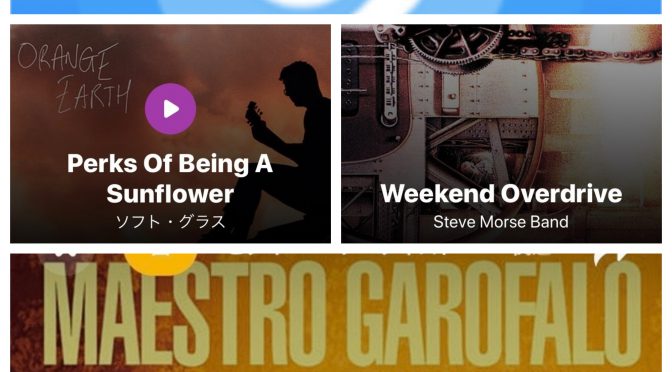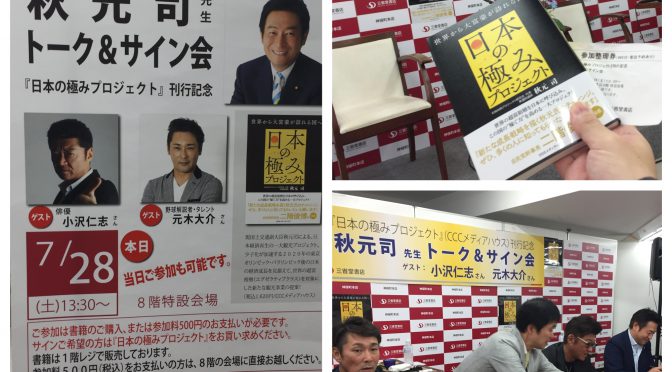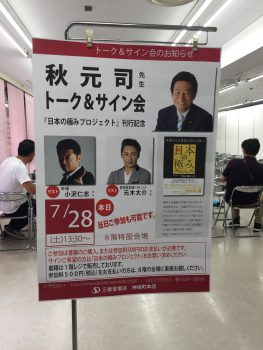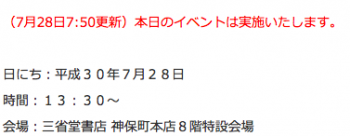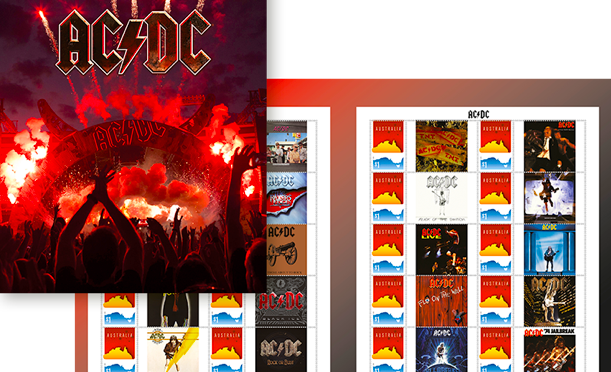ワラタス、スーパーラグビー2018プレーオフ準決勝で敗退
” 南アフリカのジョハネスバーグ(エミレーツエアライン・パーク)で7月28日、スーパーラグビーの準決勝第2試合がおこなわれ、
悲願の初優勝を目指す南アのライオンズがオーストラリアのワラターズに44ー26で競り勝ち、3年連続の決勝進出を決めた。
準決勝第1試合では、ディフェンディングチャンピオンのクルセイダーズがハリケーンズとのニュージーランド勢対決を制しており、決勝は2年連続同じカードとなった。
先に主導権を握ったのは、4年ぶりの王座奪還を目指したワラターズだった。
序盤からハンドリングミスなくボールを動かし敵陣でプレーし続け、4分、ハイボールをはさんでさらに連続攻撃し、CTBカートリー・ビールの飛ばしパスから数的優位をつくってFLネド・ハニガンがゴールラインを割った。
8分にはWTBタンゲレ・ナイヤラヴォロのビッグゲインでチャンスとなり、たたみかけてFBイズラエル・フォラウがフィニッシャーとなった。
しかしライオンズは21分、チームアタックで敵陣22メートルラインまで攻め上がると、
今大会終了後にヤマハ発動機ジュビロへの新加入が決まっているFLクワッガ・スミスが力強い足腰でゴールに持ち込み、流れを変えた。
26分には、カウンターを仕掛けたWTBアピウェ・ディアンティがチップキックしたボールを自ら確保して50メートル以上走り切り、連続トライ。
35分にはラインアウトからドライビングモールで押し込み、ゲームをひっくり返した。
だが、ワラターズも食い下がり、39分、ラインアウトからのサインプレーが決まってPRトム・ロバートソンが走り抜け、同点トライ。19-19で前半を終えた。
後半先に得点したのはライオンズで、55分(後半15分)にPGで勝ち越す。
さらに、ワラターズにイエローカードが出て数的有利となった直後の58分には、得意とするラインアウトからのモールで追加点を奪い、27-19とした。
ライオンズの勢いは止まらず、63分には再びFLクワッガ・スミスがギャップを突いてゴールへ走り切り、SOエルトン・ヤンキースのブーツでも加点してリードを広げた。
76分にワラターズのSHジェイク・ゴードンがトライゲッターとなってコンバージョンも決まり、11点差となったものの、
数分後、自陣深くから攻めようとしたワラターズがパスを乱してライオンズボールとなり、SOヤンキースのクロスキックからWTBコートナル・スコーサンがダメ押しトライを決め、激闘は決着がついた。
2018年のスーパーラグビー王者を決める決勝は、8月4日にクライストチャーチ(ニュージーランド)のAMIスタジアムでおこなわれる。”(出典:RUGBY REPUBLIC)
続きを読む オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所:ワラタス、スーパーラグビー2018プレーオフ準決勝で敗退 →