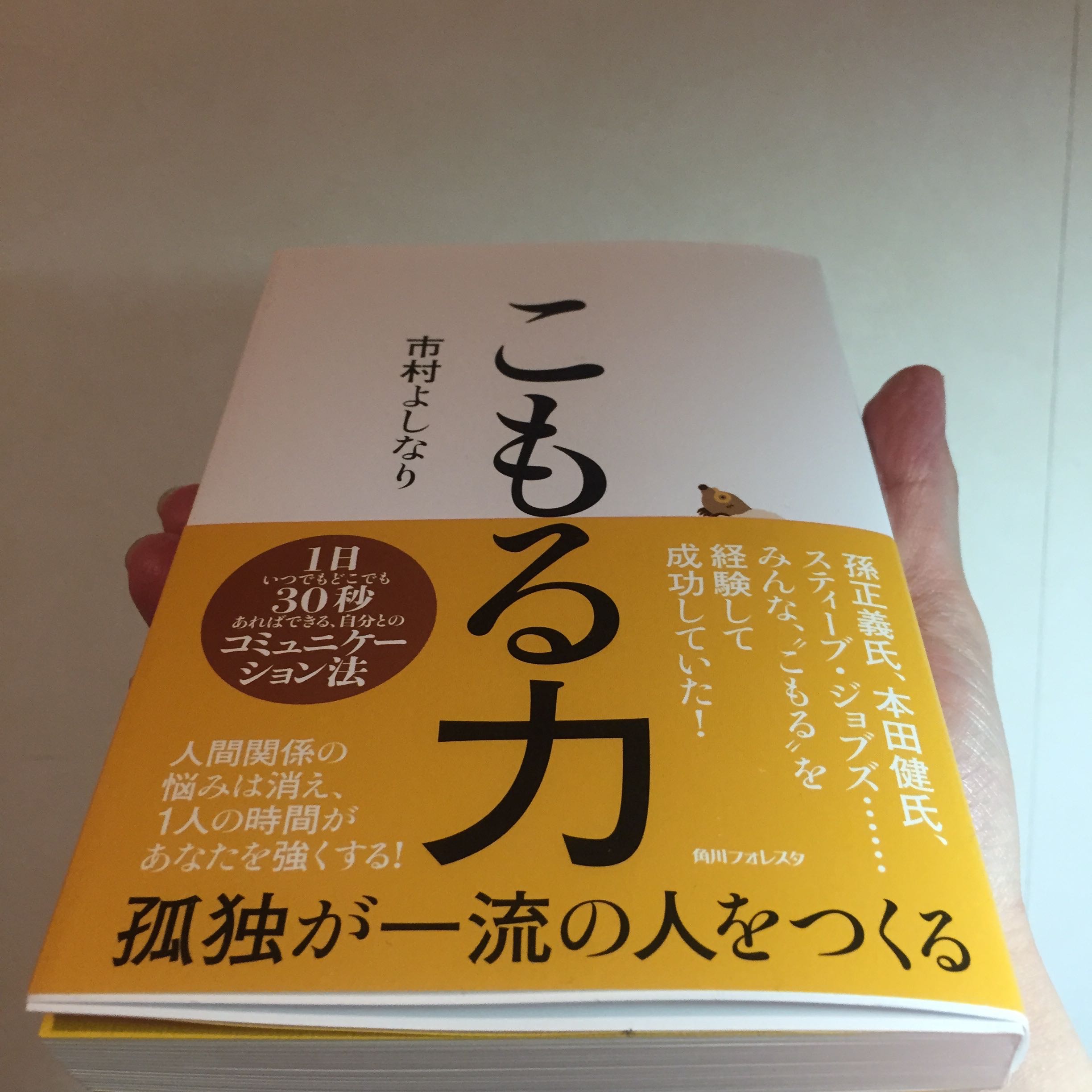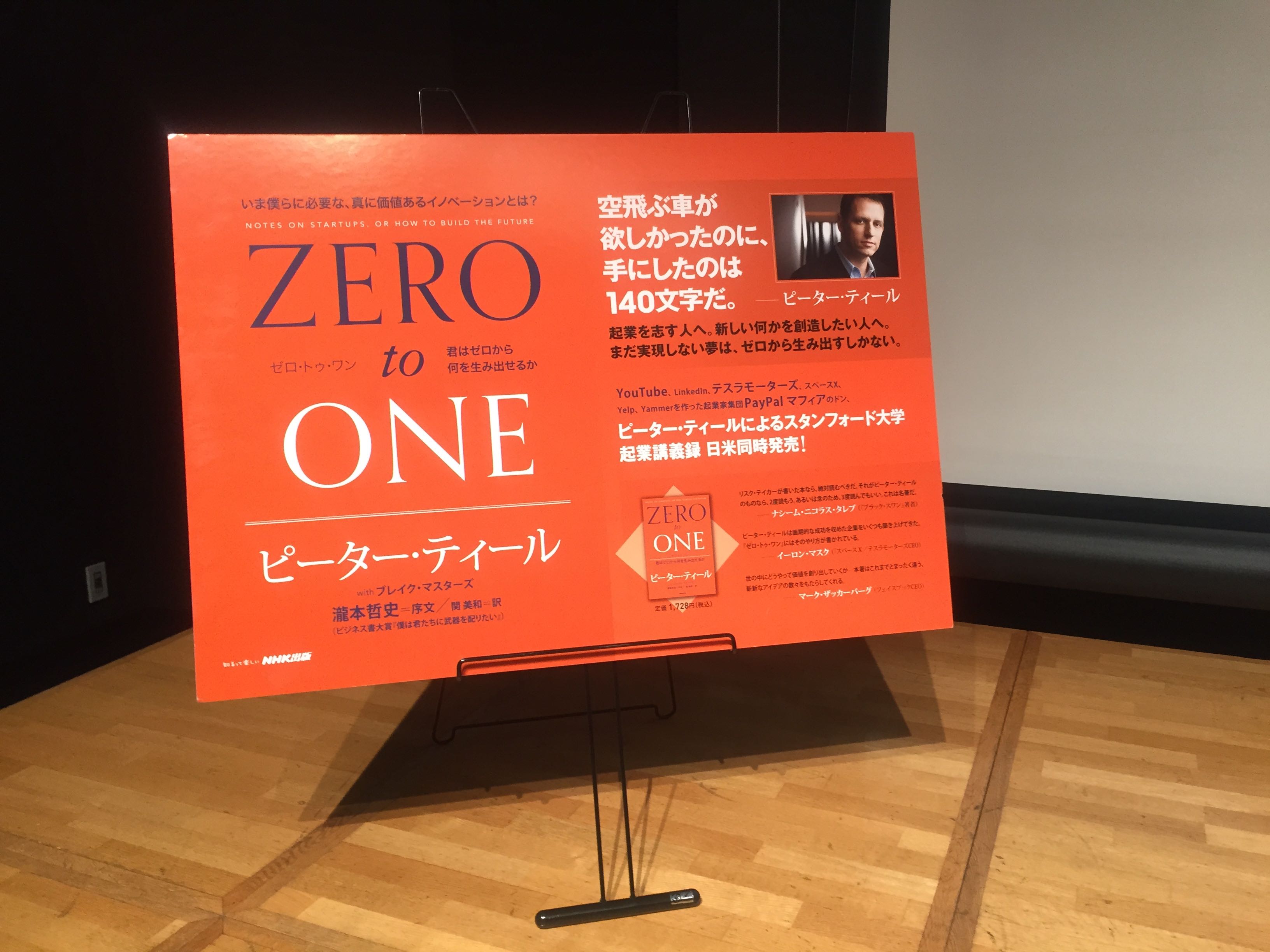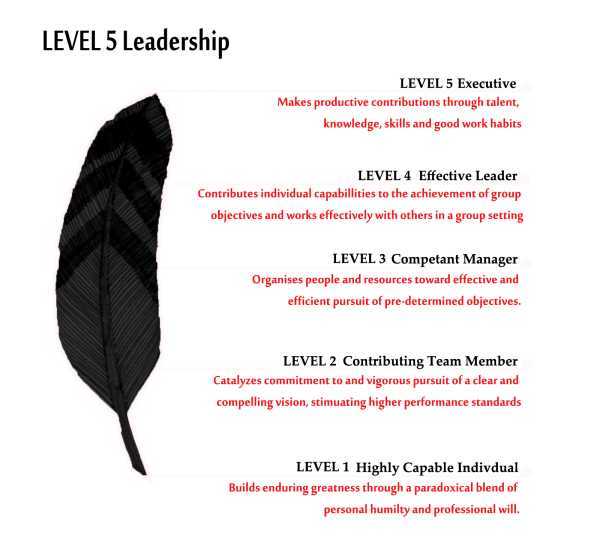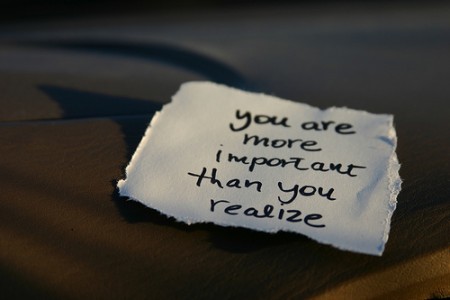田原総一朗さんの『起業のリアル』を読了。
>> 田原総一朗さんがLINEやスタートトゥデイから起業家の成功に迫る対談集:『起業のリアル』中間記 <<
後半に登場する起業家は
リブセンス 村上社長 // テラモーターズ 徳重社長 // innovation 岡崎社長 // リビング・イン・ピース 慎代表 // ティーチ・フォー・ジャパン 松田代表 // ベレフェクト 太田代表 // ディー・エヌ・エー 守安社長 // サイバーエージェント 藤田社長 // 特別対談:堀江貴文
といった目次立て。
正解のない時代の課題設定
この中で印象的であったのは、田原さんとティーチ・フォー・ジャパン松田代表のやり取りで
田原:いまの学校の一番の欠陥は、正解のある問題の解き方した教えないことですよ。見えない社会で必要なのは、むしろ正解のない問題に対応する力、
もっといえば問題そのものを見つける力です。そういう意味では課題解決より課題設定でしょう。
松田:おっしゃる通りで、私も課題解決と同時に課題を発見していく力は必要だと考えています。
田原:これは日本の昔からの課題ですよ。僕は日本の教育について、宮沢喜一や橋本龍太郎といった歴代首相と議論したことがある。
そのとき彼らがいっていたのは、国際会議で欧米の大臣は積極的に発言するけど、それと比べて日本の総理や財務大臣は発言が少ないということ。
なぜ発言しないのかというと、間違いを恐れているからです。日本の教育は正解のある問題ばかり解かせてきたから、口をつぐんでしまうのです。そのあたりはどう思う?
松田:日本とアメリカの両方で高等教育を受けたので、その差は肌で感じています。日本だと、教室は理論を教えてもらうところですよね。
一方、アメリカでは毎週、授業を受ける前に五00ページ分くらいの論文の束を渡されて、理論を頭に叩き込んでこいといわれます。
授業は理論を使って議論する場所。それぞれが自分の意見をぶつけ合うということが非常に重視されていました。(71%/百分率は紙の本でいうところのページ数に相当/以下同様)
この主張は前回の引用と同様、またしても先週受講した藤原和博さんの主張と一致する内容です。
>> 藤原和博さんが教えてくれた「それぞれ一人一人」の時代の「稼ぎ方」:神田昌典ビスネスプロトタイピング講座 その壱 <<
藤原さんの論旨は、” 正解をいち早く言い当てる力 ” が、学校教育で今も昔も重視されているが、今の時代は
情報編集力 : 自分の考えを他人と触れさせ、修正していく力、「正解主義」→「修正主義」が求められているとおっしゃってました。
この部分、徳重社長も類する事に言及されており
” 向こう(アメリカ)では頭のいい人ほどクレイジーで、大きなことをぶちあげるんです。一方、日本は頭のいい人ほどロジカルで、大きなことをいわない。だから優秀な人がベンチャーに流れてこない。” (53%)
頭の中が「正解」を追い求めていたり、そこに縛られている限り、本来、備わっている力を引き出す事は導けない事を意味するのかもしれません。
ポスト・ホリエモン時代の感覚
その他では・・
村上社長:” 不便や問題を解決するのがビジネスの基本です。” (48%)
慎代表:” 努力は根底に自分を愛せる心がないとできないと思います。” (66%)
” 相手から感謝されるかどうかを気にしていたら、自分が正しいと思ったことができなくなる。
誰も評価してくれなくても、自分がやりたいと思ったことや、いいと思ったことをとことんやる。そう心がけています。” (68%)
田原: “巨万の富を得られる力を持ちながら、それを社会のために使うというのは、いまの若い世代を象徴する働き方の一つだと思う。” (69%)
といったところに刺さりが。
従来型日本企業からポスト・ホリエモン型へ
本の最後では田原さんが「あとがき」で、(従来型の)日本企業が如何に競争力を失ったかについて分析がなされていて
” 僕(田原)は要因が二つあると思う。一つは、よく言われているように、競争相手が増えたということだ。かつては価格の安さと品質の良さがメイド・イン・ジャパンの売りだったが、
韓国や台湾、中国といった国々が品質の良いものを日本企業より安い価格でつくるようになった。
もう一つ、日本的経営が負の要因になったことも大きいだろう。日本的経営は、終身雇用、年功序列で、社員の面倒を一生見ていく。
マルクスは労働者を商品でなく人間として扱うべきと説いたが、日本企業は社員を家族として面倒を見た。
大企業になると、企業年金にとどまらず、社宅や保養所まで、本当に手厚い福利厚生があった。企業が家族的な経営をしてきた背景は二つある。
一つは、高度成長で企業に余裕があったこと。もう一つは、労働組合への対抗だ。
日本の労働組合は、戦前は共産党系が、戦後は社会党系が強かった。そのため企業は、社会主義や共産主義の組合が理想とする社会より、
資本主義社会のほうが豊かで安心できることを社員に示す必要があった。
つまり企業は、労働組合に社員を奪われまいとして福利厚生に力を入れたわけだ。
これは非常にうまくいった。家族的経営のおかげで社員は愛社精神を持ち、多少の無理もいとわず会社のために働いた。だから日本企業は世界で勝つことができた。
ところが、冷戦が終わって、潮目が変わった。共産主義・社会主義国が瓦解すると、労働組合もイデオロギー的基盤を失って弱体かした。
そうなると、企業は労働組合とはりあう必要がなくなり、株主の利益を増やすことばかり考えるようになる。
社員は代替可能な部品に過ぎず、賃金はできるだけ安いほうがいいと経営者が考えるようになったのも、おそらくこのころからだ。
冷戦の終結によって、企業が日本的経営によって社員をつなぎとめる必然性が薄れ、それまで隠れていた資本主義の本質がむきだしになっていったのだ。” (97-98%)
時代に感覚を馴染ませてくれる一冊
この本では新しい企業体の担い手、最後で衰退の一途を辿る従来型の企業体について言及され
それを読めば時代は移ろい、進んだ時計の針が元に戻る事はないであろう事は容易に想像出来るわけで
読み手の頭の中の時代認識を再認識させ、上手に時代の感覚を取り込んでいる人たちの共通点などに光があてられ
ご自身は自伝(下記)等で生涯を振り返る限り、ディレクターとの立場を強く自認されているようですが、ジャーナリスト田原総一郎の真骨頂が伝わってくる一冊でありました。