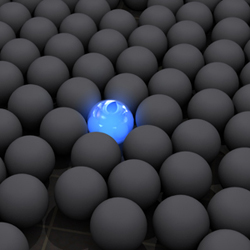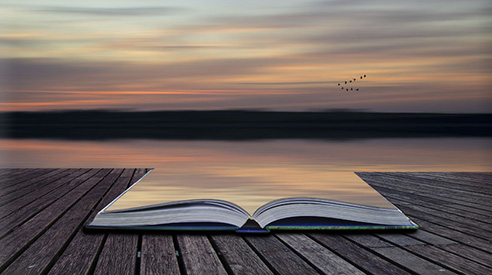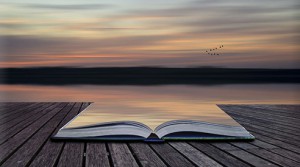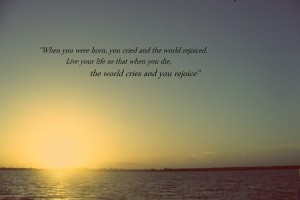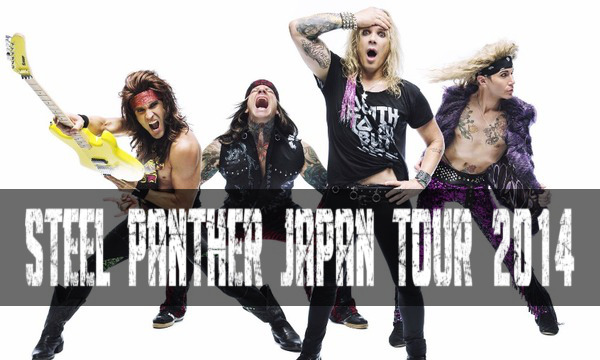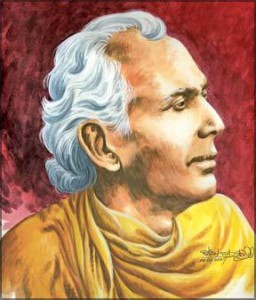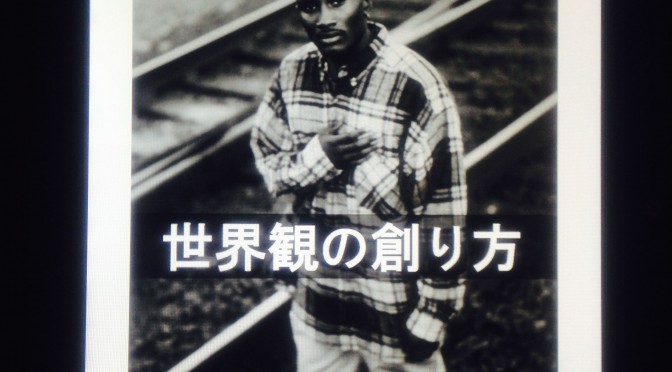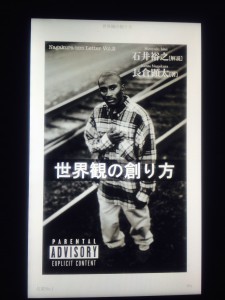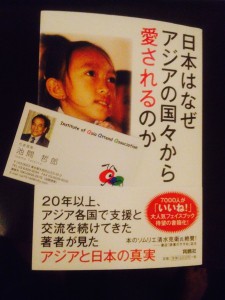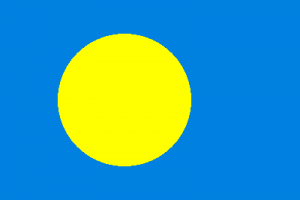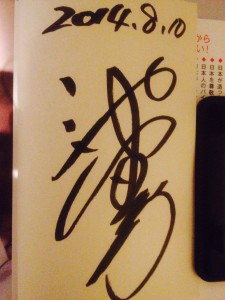前回に続いて、平秀信さんのウェビナー。このところ妙に平さんづいてるなぁ(笑)来週も1本予定しているし・・。

成功者にメンターあり
今回は平さんの師匠(メンター)の(通称)仙人さんが 新たなプログラムを提供されるとの事で、その申込前日の前夜祭。
何でも明日6時の申込を前に1万人以上が行列を成しているとかで(ホントかね?!)
約90分の間、視聴者からの質問を交え、平さんと仙人さんのやり取りに耳を傾けていました。
謎めいていながらにして、多くの人を惹き付ける仙人さんとは・・
因みに、仙人さんについては詳細が語られておらず、仙人さん主催の高額セミナー(100万円以上?)に参加すると、ご本人と面識を持てるようですが
今回のウェビナーでも、一連の「ヴァーチャル・コンサル」でも音声の出演のみ。
平さんのセミナーに長く参加されている方の間では、ミスターXの呼称でもお馴染みのようです。
それで、1万人規模の関心を集めるとは凄いですね。
現在は治療ビジネスを主に手掛けられ、若かりし頃はバス停や貧しい環境の中でルームシェアするところで寝床を得ながら、
コピーライティング等を学ばれる経歴から、現在では億単位の稼ぎを叩き出されるまでになったそうです。
特異な人生経験から築かれた独自の人生観
仙人さんの愛称となる由来は、もともと小さい頃から山奥、自然の中で暮らすライフスタイルに憧れていたそうで
学校教育は中学の頃に早々にドロップアウトして、上記のようなそれこそストリートであるとか、過酷な状況から単身這い上がって、独自の人生観を身につけられ、
そこが平さんをはじめとして、百万円単位の高額セミナーの開催であったり、多くの信奉者を得る事につながった。
女性にモテたいは、男性の大きな動機付けとなる
お金持ちになりたいと思ったキッカケは、経済的に困窮している時代に好きになった女性に
「高学歴か高収入でないと一緒になれない」と言われた事によって。最初は海外のオークションサイトで、家賃や食費を稼ぐところから
特異な経験をeブックという形にまとめ、徐々に稼げる金額を拡大。
やがて$20で買ったジェイ・エイブラハムのカセットテープから時給50万円の世界を知り、
指が曲がるまで日々ひたすらコピーラインティングの勉強と、インターネットビジネスについて学び、成功に二文字を近付ける事に。
テクニックの前に立つ、強烈なる思ひ
コピーラインティングの勉強では先生が居たようですが、テクニック云々の前に、書き続ける事の大切さ、メンタル面の強化を学んだ。
この辺、自分のやっている事に如何に没頭出来るかの資質が問われますね。
仙人さんは、資産構築の分野でも多くの人に教えを説く立場で、これはお金に限った事ではなく、自分の価値観、やりたい事によって、何が必要となるかを見極める事が大切。
特に仙人さんが自身の人生で実感した事は、人は自分のために頑張れる事には限界があるが、誰か、この人のためと思った/決めた人たちのためには思った以上の力が出せるという事。
成功の決め手は、心の声に耳を傾けた事
仙人さんが経済的に成功を収めた自身の分析に、特別な才能は無かったが、
「自分の心を声を聞く」事を大切にしていた事が、たった一つ才能と言えたかもしれないと。
ウェビナーを受講していた人たちにも、誰にでも心のどこかに声はしているので、少しでも良いから「心の声に耳を傾ける」事を習慣にしていった方が良いと助言。
自分に自信がないと心の声を聞きづらいが、本来、誰も自信がないもの。恥ずかしさを捨ててから、どこへ行っても自分を出せるようになるものだと。
人は一人で変われず、環境と共に変わる
また、心の声を聞くためには、普段、自分が身を置いている環境が大事で、周りの人、先生、メンターを如何に持てるか
自分がそういった人たちに影響を受けて行く事が大切。
ウェビナーではミラーニューロンの話しを交えて説明されていましたが、自分自身にだけ目を向けるのではなく、周囲に目を向ける事も欠かさざるべき事なりと。