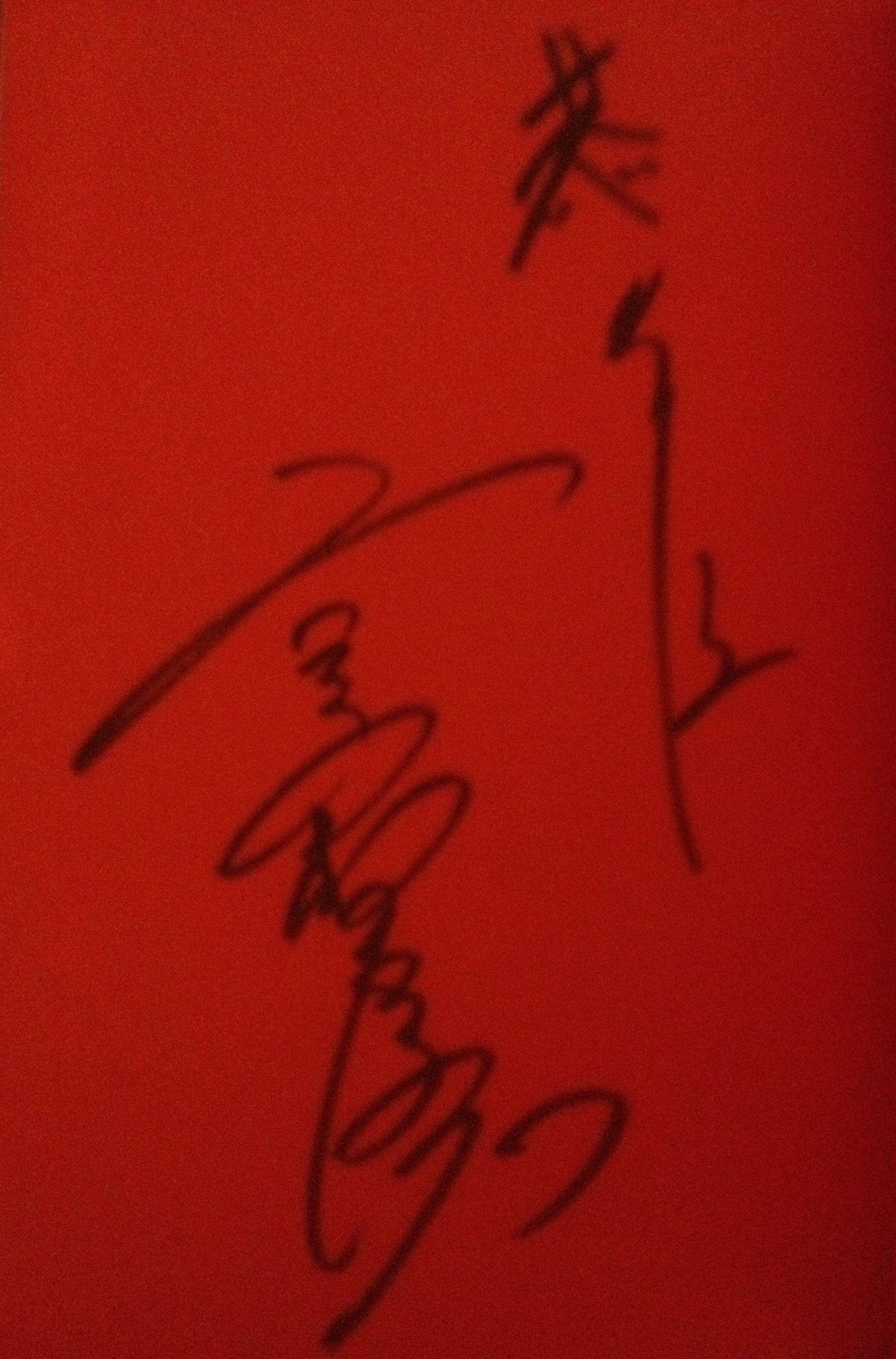先週、中間記⬇︎をアップロードした
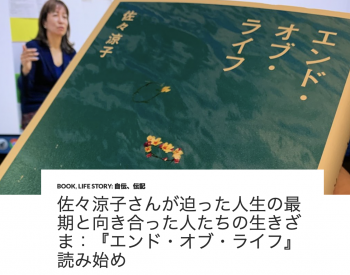
ノンフィクション作家 佐々涼子さんの『エンド・オブ・ライフ』を読了。
最期の日々、そして在宅医療という選択肢
本書の骨子を「あとがき」から拾うと
” この本は、各章でも記している通り、二〇一三年から二〇一九年まで在宅医療で出会った人々を取材し、その姿を書いたものだ。”(p313-314)
その立脚から、さまざま患者が最期に至る日々について綴られています。
” 「主治医がどれだけ人間的であるかが、患者の運命を変えてしまうんですよ」”(p221)
或いは
” 予後告知は医師がするものではない。患者自身が感じているものを引き出すのだ。人間は、どこかで自分の死期を予期する能力があると、早川は感じている。
・・中略・・
もしこの人なら精神的に耐えられる、この家族だったら患者を支えられる。そう判断したら、できるだけ意識を清明に保つようにします。”(p234)
と医師により大きく左右される現実に環境に。
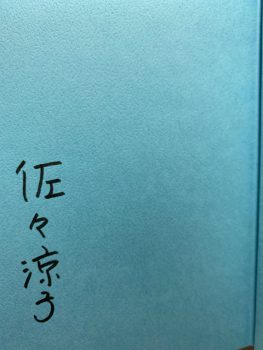
テーマとなっている在宅医療について
” 少しでも人間らしい医療がしたくて、彼女は在宅医療の医者になった。在宅医療は医師の裁量が勤務医よりも大きく、患者も自由度が高い。もちろん医師の知識や経験が未熟なら、患者は不幸である。”(p228)
本の主人公で四八歳にして、ステージIVのガン宣告を受け、在宅医療を選択した森山文則さんは
” 「これこそ在宅のもっとも幸福な過ごし方じゃないですか。自分の好きなように過ごし、自分の好きな人と、身体の調子を見ながら、『よし、行くぞ』と言って、好きなものを食べて、好きな場所に出かける。病院では絶対にできない生活でした」”(p263)
といった内容が実態や経験談などから、光と陰といった様相を呈しながら迫られています。
最期まで生き抜くということ
在宅医療ということについて考えたことは無く、知識もなかったところ、読書を通じ意識するに良いきっかけとなりました。
全体を振り返ると、森山文則さんの死と対峙し
” 自分がこの世からいなくなることや、自分という存在が何にもなくなってしまう、漠然とした恐怖がふっと湧いてきて、そういうのを大声でかき消したくなることがあったけど。・・・この病気になると、そういう気持ちがなくなるって話をしたよね。
それはたぶん、漠戦としているから、怖かったんやと思う。死というのもが、誰よりも早く、自分の身に降りかかってきた時には、それは恐怖じゃなくなくなる。
・・中略・・
漠然と恐れていたものが、具体的に見えてくるんだよね。自分の持っている恐怖の正体がはっきり見えた時、人はどこかほっとするんやろうね」”(p269)
と表した心情に、佐々涼子さんが本書を書き上げる至った取材を通じ得られた
” 大切な人を大切に扱い、他人の大きな声で自分の内なる声がかき消されそうな時は、立ち止まって耳を澄まさなければ、そうやって最後の瞬間まで、誠実に生きていこうとすること。それが終末期を過ごす人たちが教えてくれた理想の「生き方」だ。”(p314)
「生」に対する学びなど強く刺さってきた箇所で、
テーマは「死」に絡むだけに自分が日ごろ読んでいるテーマの中でも重たいですが、登場する方々の多くの最期へ向かう姿勢が前向きで読後、読み応えとして心に響いてきました。